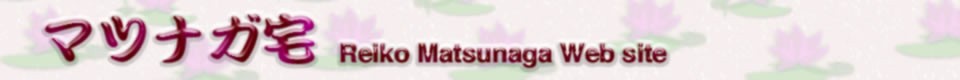「インターネットのホームページに載せるので、アタシを誉める文章を無報酬で書け」
という突然の要求に驚いて訪れると、すでに22人もの関係者がこの一方的な要求を受け入れて文を寄せていることが分かり、さらに驚かされた。それぞれに忙しかろうに概ねかなりの行数を費やして、曰く、魔性の女、芸達者で性格が強くて本能的でお利口でジュンサイ、極道者、複雑怪奇、肝が据わっている、フェロモン女優、腹黒い、クール……。これじゃあ何がなんだか分からない。ジュンサイってのも分からないけど。ヌルリっとした性格だとか、そういう意味なのか?
自分はというと、すでに同様の感想もいくつか掲載されているが、特段親しくしているわけでもないのになぜオレに、という思いでいる。ケラリーノ・サンドロヴィッチ氏らによる新結成ユニット、オリガト・プラスティコの第1回公演『カフカズ・ディック』稽古中の今、稽古後の飲み屋を何度か一緒したが、始め1~2杯ビールを飲んだあとはずっとウーロン茶をオーダーし、決して隙を見せようとしない。まあ、初めての飲みの席で私の方が調子に乗りすぎ、早々につぶれてしまったものだから、こんなヤツと酒席を共にしたところで得るものはないと見切られた可能性は十分にあるのだけれど。
こんどの芝居で私が演じるのは、タイトルロールのユダヤ人実存主義作家(とされる)フランツ・カフカ。彼女は、カフカ最晩年のごく短い期間交際し、最期を見とった恋人役を演じる。当然、芝居の中でふたりの愛情を描くシーンが(残念ながらホンの一瞬にすぎないが)あるのだけれど、なかなかしっくりとこない。距離感を掴みかね、今ひとつ踏み込めずにいる様子だ。もちろん、多くの知己から賢く、勘がよいと太鼓判を押されている彼女のこと、本番までにはきっちりと結果を出してくれるものと確信しているが、一方で評される、肝が据わっているとか性格が強いとか、そういう印象はあまり受けない。例えて言えば、友好的かつ自信に満ちた笑顔を浮かべる彼女の姿の、その精巧な絵が描かれた盾の裏側に身を潜め、ある種の警戒と緊張を決して解くことなく小さな覗き穴から相手を観察している、そんなイメージが思い浮かぶ。
この種の自己防衛的演技は誰でもすることだ。私なんぞは盾どころではない。にこやかに笑いながら握手の手を差し出す己の姿をコンクリート製の土管の表面に描き、自分はその細い土管の中に入って身を守っているのである。もちろん覗き穴はしっかり仕込み、相手の観察は怠らない。だが、やはり土管では具合が悪い。攻撃に転ずることができないし、機動的にポジションを変えることも不可能。強敵が現れたら息を殺して通り過ぎるのを待つだけだ。
彼女の場合はさらに、盾に描かれたその自画像を、相手によって様々に掛け替えているのではないかと思う。巧妙な戦略である。彼女についての証言が人によって大きく異なるのは、きっとこのためなのだ。もしかすると、私がイメージした盾の裏側から相手を観察する彼女の姿も、ほかならぬその盾に描かれた虚構の肖像なのかもしれない。正体を見抜いたつもりになっていて実はそんなまやかしの姿を見ているのだとすれば、それはまさに私がドカン人間だからだ。
社会に、自己を映し出す鏡は他者の存在としてしかない。相手を知ろうとする行為を通じて、自分自身について知り、知らされる現実が常にある。彼女の場合、その自分自身を知らしめる度合いが世間一般の人よりほんのちょっと大きいのだろう。彼女の印象としてまた多く一致するところの、どこか謎で、捕らえどころのなさ、そして彼女を知るおそらくほとんどの人が、彼女を興味深く思い、好意を持つ事実は、これと無関係ではないはずだ。自己への探求は(きわめて困難であるものの)誰にとっても抗しがたい不可思議な力によって引き寄せられる課題である。この稽古の押し迫った時期に、おまけに何の見返りもなくこんな要望を引き受けて
しまうのも、つまりそういう理由からなのだ。